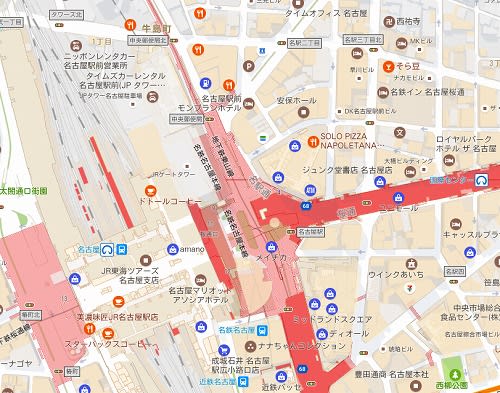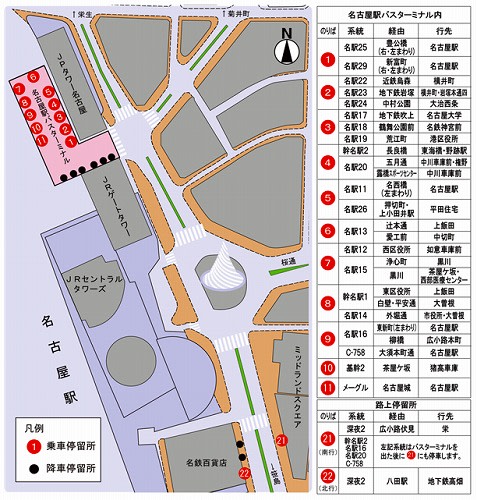この週末は、土曜日が3月11日とあって、東日本大震災の被災地各地では慰霊祭が行われました。
その中のうち仙台市南部の地域の慰霊祭に行かれた方の話には、ハッとする所がありました。
悲しい話は数多くありますし、かつて神戸市でも多くの話を伺いました。
東日本大震災は、津波による被害があまりにも特徴的です。
地震動による建物崩壊よりも、この津波の陸上浸出による建物崩壊です。
この津波被害により、今の我々でも東北地方の海岸地域に、「津波てんでんこ」という言葉があるを知りました。
津波では、各々が自身を守って、さっさと逃げる、という意味です。
三陸地方では、地形の特徴から繰り返し津波に襲われたこともあり、こうした言い伝えがありました。
しかし仙台平野南部では近代に入り、堅牢な海岸堤防が造られたこともあり、津波が忘れられた面も否定できないかった、という一面があるそうです。
あの日までは。
その6年前のその日、大きな地震が起きました。
地震の数分後、津波警報が発表され、数度の波高が訂正する発表があったところへ、予想外の津波が実際に襲来。
翻って考えれば、今この地域に住んでいる者は、たまたま東日本大震災には遭っていないだけで、地震による災害(震災)前であるとも言えるのでは、というお話。
東日本大震災の災害エリアではなかっただけで、仮に憂慮されている南海トラフによる巨大地震があれば、東海地方の海岸近くにいた者がさっと逃げられるか、というお話です。
以前に弊ブログではこんな記事を書きました。2016年7月29日投稿:『前』はなかなか分からないものだが
この時の記事主眼は、交通事故を取り上げ、気を付けていて防ぐものではなく、普段の行動の中に事故を起こす要素があるもので、事故はおきてから初めてその『事故前』が分かるもの、という内容です。
この『前』には、災害、特に震災『前』も含まれることに気づきました。
東海地方の人々、特に海岸に近い人の中には、6年前の東北地方の被災地域のような状況かもしれません。
南海トラフによる巨大地震は、東日本大震災と同様に、巨大な津波が襲来すると予想されています。
しかも東日本大震災では、地震の海底が動いた津波の波源域が海岸からある程度離れていたため、襲来には約10分の差がありました。
しかし南海トラフによる地震では、震源域が陸上に近く、したがって波源域も海岸線に近いため、地震発生から数分の後に襲来すると予想されています。
東日本大震災を他山の石とせずに、今只今は『震災前』なのかもしれないと、弁えることが大切だということをつくづく思いました。
ちなみに、南海トラフによる地震だけでなく、海溝の地盤の動きによる地震は巨大な地震になりがちですが、さらにその地盤の動きがゆっくりだと、いわゆる「地震動」は陸上で感じられる揺れは少なくなり、そのエネルギーは津波に与えられることとなって、「あまり揺れなかったけど、巨大な津波だった」ということも起こります。
いわゆる「津波地震」というものです。
これ、陸上での揺れ(震度)は本当に小さめになり、しかし信じられないような津波。
小さな揺れだと、果たして津波襲来を予想できるか。実際には気象庁から地震があれば津波情報が発表されますが、発表されてからでは遅く、海岸に近い地域では地震動を感じれば、直ぐに逃げねばなりません。
備えあれば憂いなし、こうしたことに日ごろから備えておくことが肝要、ということを改めて感じた次第です。
その中のうち仙台市南部の地域の慰霊祭に行かれた方の話には、ハッとする所がありました。
悲しい話は数多くありますし、かつて神戸市でも多くの話を伺いました。
東日本大震災は、津波による被害があまりにも特徴的です。
地震動による建物崩壊よりも、この津波の陸上浸出による建物崩壊です。
この津波被害により、今の我々でも東北地方の海岸地域に、「津波てんでんこ」という言葉があるを知りました。
津波では、各々が自身を守って、さっさと逃げる、という意味です。
三陸地方では、地形の特徴から繰り返し津波に襲われたこともあり、こうした言い伝えがありました。
しかし仙台平野南部では近代に入り、堅牢な海岸堤防が造られたこともあり、津波が忘れられた面も否定できないかった、という一面があるそうです。
あの日までは。
その6年前のその日、大きな地震が起きました。
地震の数分後、津波警報が発表され、数度の波高が訂正する発表があったところへ、予想外の津波が実際に襲来。
翻って考えれば、今この地域に住んでいる者は、たまたま東日本大震災には遭っていないだけで、地震による災害(震災)前であるとも言えるのでは、というお話。
東日本大震災の災害エリアではなかっただけで、仮に憂慮されている南海トラフによる巨大地震があれば、東海地方の海岸近くにいた者がさっと逃げられるか、というお話です。
以前に弊ブログではこんな記事を書きました。2016年7月29日投稿:『前』はなかなか分からないものだが
この時の記事主眼は、交通事故を取り上げ、気を付けていて防ぐものではなく、普段の行動の中に事故を起こす要素があるもので、事故はおきてから初めてその『事故前』が分かるもの、という内容です。
この『前』には、災害、特に震災『前』も含まれることに気づきました。
東海地方の人々、特に海岸に近い人の中には、6年前の東北地方の被災地域のような状況かもしれません。
南海トラフによる巨大地震は、東日本大震災と同様に、巨大な津波が襲来すると予想されています。
しかも東日本大震災では、地震の海底が動いた津波の波源域が海岸からある程度離れていたため、襲来には約10分の差がありました。
しかし南海トラフによる地震では、震源域が陸上に近く、したがって波源域も海岸線に近いため、地震発生から数分の後に襲来すると予想されています。
東日本大震災を他山の石とせずに、今只今は『震災前』なのかもしれないと、弁えることが大切だということをつくづく思いました。
ちなみに、南海トラフによる地震だけでなく、海溝の地盤の動きによる地震は巨大な地震になりがちですが、さらにその地盤の動きがゆっくりだと、いわゆる「地震動」は陸上で感じられる揺れは少なくなり、そのエネルギーは津波に与えられることとなって、「あまり揺れなかったけど、巨大な津波だった」ということも起こります。
いわゆる「津波地震」というものです。
これ、陸上での揺れ(震度)は本当に小さめになり、しかし信じられないような津波。
小さな揺れだと、果たして津波襲来を予想できるか。実際には気象庁から地震があれば津波情報が発表されますが、発表されてからでは遅く、海岸に近い地域では地震動を感じれば、直ぐに逃げねばなりません。
備えあれば憂いなし、こうしたことに日ごろから備えておくことが肝要、ということを改めて感じた次第です。