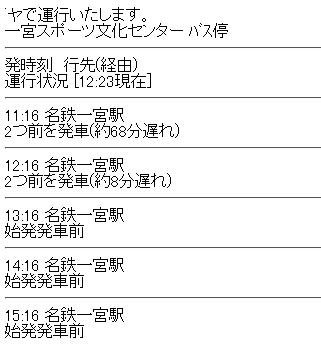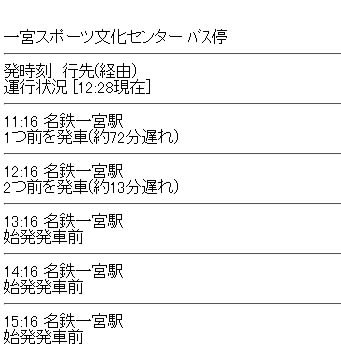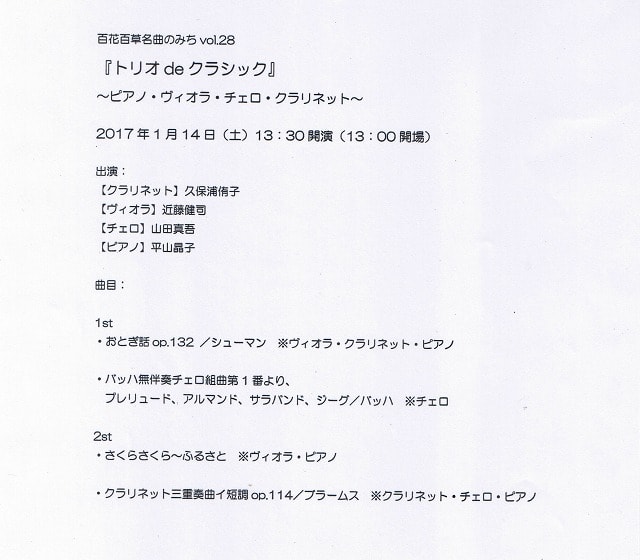先般、ツイッターでもリツイートされ、テレビワイド番組でも話題になっておりましたが、某宅配の配達員が、配達先不在によりいらついていたのか、荷送用の台車を投げ捨て、さらに持ち帰り荷物と思われる物品を投げ、さらに蹴とばす様子を捉えた動画が公開され、問題行動として話題にしておりました。
この宅配運送事業者に問い合わせたところ、社の正社員とのことで、配達先が不在で、さらに何かとイライラが重なり、このような行動に至ったとのこと。
配達員の行動も問題ですが、番組で言及するには宅配の環境の悪化もあるのでは、と。
その中に配達を受ける先のお宅にも問題。
不在票を入れるも、なかなか反応が無かったり、再配達依頼の指定時刻に不在となったり、さらには、宅配需要の増大も。
宅配需要は、通販の急激な増加で、宅配扱い量が兎に角急増。
生鮮食料品以外は殆ど通販ばかりで購入しているという人もいるそうで、通販での購入を行わない私にとっては、とても異次元の世界。
おそらく、通販で宅配を利用している人は、年間どころか、月間で何度も利用しているのでしょうね。
私には信じられません。パソコンどころかスマホの普及で、自宅のそれこそ何でもない部屋の一室で「あれ欲しい」と発注をかけて、品物を買い寄せる行為。
便利だけの一点で、通販利用。
その陰で宅配運送事業者は大変な思いをしているわけです。
スマホの普及と同じく、宅配扱い量が急増しているそうで、通販を利用しない私としては、このユーザーの便利だけで通販。寒い中を届けてくださっているわけで、受け取り人の中には、配達される人にアゴで使うが如くの行動をされる方もいるそうで、そんなのが重なれば、配達員のイライラも重なるのかもしれません。
少なくとも、配達された方には、労いの言葉の一つもかけたいと思います。
それができる方が、通販を利用できる方だと思います。
この宅配運送事業者に問い合わせたところ、社の正社員とのことで、配達先が不在で、さらに何かとイライラが重なり、このような行動に至ったとのこと。
配達員の行動も問題ですが、番組で言及するには宅配の環境の悪化もあるのでは、と。
その中に配達を受ける先のお宅にも問題。
不在票を入れるも、なかなか反応が無かったり、再配達依頼の指定時刻に不在となったり、さらには、宅配需要の増大も。
宅配需要は、通販の急激な増加で、宅配扱い量が兎に角急増。
生鮮食料品以外は殆ど通販ばかりで購入しているという人もいるそうで、通販での購入を行わない私にとっては、とても異次元の世界。
おそらく、通販で宅配を利用している人は、年間どころか、月間で何度も利用しているのでしょうね。
私には信じられません。パソコンどころかスマホの普及で、自宅のそれこそ何でもない部屋の一室で「あれ欲しい」と発注をかけて、品物を買い寄せる行為。
便利だけの一点で、通販利用。
その陰で宅配運送事業者は大変な思いをしているわけです。
スマホの普及と同じく、宅配扱い量が急増しているそうで、通販を利用しない私としては、このユーザーの便利だけで通販。寒い中を届けてくださっているわけで、受け取り人の中には、配達される人にアゴで使うが如くの行動をされる方もいるそうで、そんなのが重なれば、配達員のイライラも重なるのかもしれません。
少なくとも、配達された方には、労いの言葉の一つもかけたいと思います。
それができる方が、通販を利用できる方だと思います。