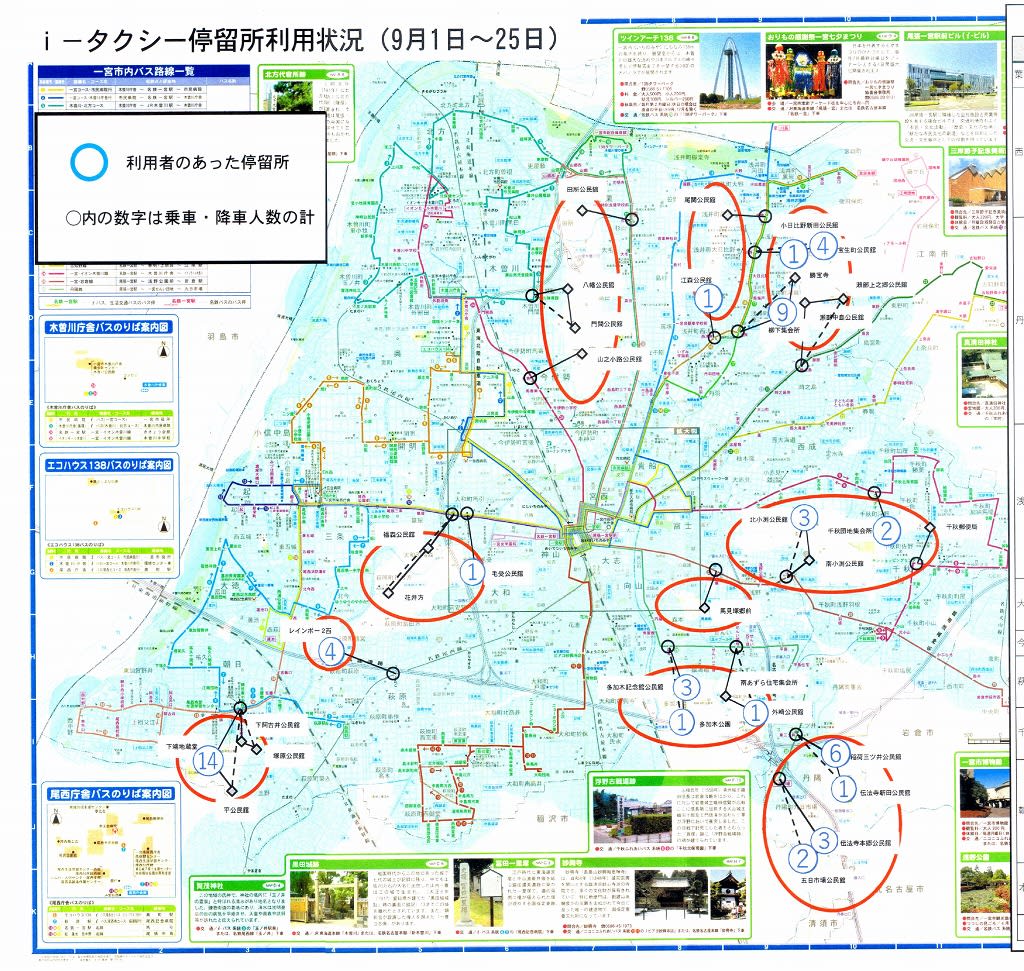昨日は、お世話になっているピアニスト鬼頭久美子さんも主催の一人である演奏会に行ってまいりました。
音楽を身近に親しんでいただこう、という趣旨で、NPO法人カプリスをお仲間と立ち上げ、その活動で子供たちに本物の音楽に触れてほしい、ということで本日、演奏会がありました。
雨で出られるかどうか気をもんでいましたが、何と、ギリギリの時間になって、雲の流れが暫く降らないであろうと判断できるになり、本日の予定を決行。
会場は名古屋市某所のKKホール。
建物の入口に出ていた案内板。
本来は歩道際まで出すものですが、雨の恐れがありましたので屋内に避難。
![]()
頂いた本日のプログラム表紙。
![]()
演奏者紹介。
![]()
本日の演奏曲目。
![]()
この他に、第一部と第二部の間の休憩時間に、私がリクエストした、ショパンの遺作ワルツ第17番、アンコールのような全員で合唱の、memoryを演奏でした。
凄かったのが、4曲目のファルボのカンツォーネ。バリトンの加藤さん、バリトンの単独唱和を聴いたのはこれが初めてかな。
大体20畳くらいの広さの部屋ですので、響きがガンガン。
小さい子供は泣きだす始末でした。
ソプラノやテノールは拝聴したことがありましたが、バリトンは初めての記憶。
しかもこれまでは演奏会ホールなど広い空間でしたので、なおさらに響きが凄い。
私の脳出血後遺障害で、上手く発声ができないままでいますが、このくらい発声できるようになりたいものです。
私の着席位置は、いつもの通り、最前席の一番左寄り。
この位置から眺めた写真です。
![]()
このような位置ですので、弦楽器、ヴァイオリンは目の前で演奏。
本当に目の前です。
これだけ近い位置での演奏は、こうしたプライベート空間ゆえのの演奏。
大きなホールでは、できません。
また来月にも予定されているそうですので、楽しみにしたいです。
音楽を身近に親しんでいただこう、という趣旨で、NPO法人カプリスをお仲間と立ち上げ、その活動で子供たちに本物の音楽に触れてほしい、ということで本日、演奏会がありました。
雨で出られるかどうか気をもんでいましたが、何と、ギリギリの時間になって、雲の流れが暫く降らないであろうと判断できるになり、本日の予定を決行。
会場は名古屋市某所のKKホール。
建物の入口に出ていた案内板。
本来は歩道際まで出すものですが、雨の恐れがありましたので屋内に避難。

頂いた本日のプログラム表紙。

演奏者紹介。

本日の演奏曲目。

この他に、第一部と第二部の間の休憩時間に、私がリクエストした、ショパンの遺作ワルツ第17番、アンコールのような全員で合唱の、memoryを演奏でした。
凄かったのが、4曲目のファルボのカンツォーネ。バリトンの加藤さん、バリトンの単独唱和を聴いたのはこれが初めてかな。
大体20畳くらいの広さの部屋ですので、響きがガンガン。
小さい子供は泣きだす始末でした。
ソプラノやテノールは拝聴したことがありましたが、バリトンは初めての記憶。
しかもこれまでは演奏会ホールなど広い空間でしたので、なおさらに響きが凄い。
私の脳出血後遺障害で、上手く発声ができないままでいますが、このくらい発声できるようになりたいものです。
私の着席位置は、いつもの通り、最前席の一番左寄り。
この位置から眺めた写真です。

このような位置ですので、弦楽器、ヴァイオリンは目の前で演奏。
本当に目の前です。
これだけ近い位置での演奏は、こうしたプライベート空間ゆえのの演奏。
大きなホールでは、できません。
また来月にも予定されているそうですので、楽しみにしたいです。