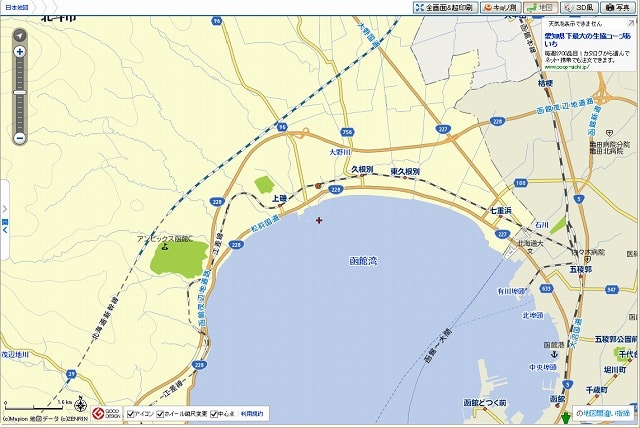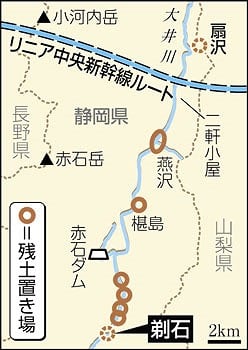3月22日中日新聞朝刊記事からです。東山動物園の北園にある遊園地で、春分の日振り替え休日の21日、観覧車の扉閉め忘れと、スロープシューターで途中で止まってしまった前車に後続の車とさらにその次の車が衝突してしまった、という二つのトラブルが続いたそうです。
記事
![]()
観覧車の搬器扉閉め忘れは、テレビのニュースで何度も伝えられました。
子供、と言っても中学生から幼児までの四人が乗った搬器、乗り場から出て行ったところを写そうとした母親が、扉が開いているのを見つけ、係員に停止を求めたものの、他のお客さんもいるから、というワケの分からない理由で、止めなかったそうです。
スロープシューターは、二人乗りの小さなエンジンの無いソリのような乗り物で、乗り物よりも少し幅の広い凹形の空間を、高低差の位置エネルギーだけで転がっていく乗り物で、レールが無いものの、凹の空間が線路空間みたいで、私の鉄ヲタエネルギーがうずうず?する乗り物です。
前を行く車が、なぜか途中で止まってしまった、ということですが、実際にあるんですね。
ジェットコースターだと、線路上に一編成しか存在しないか、或いは乗り場から出て行った編成が到着するまで、別の編成が出発できない構造なのですが、このシューターでは、特に「閉塞」のようなものは無く、時間間隔で乗り場から随時発車します。
前記の通り、鉄ヲタ精神で見ていると、「もし途中で止まってしまったら、後続車は衝突するしかないな」、と思いましたが、本当にそんなことが起こってしまいました。
ただ衝突、といっても走行速度はかなりゆっくりで、目測4km/h程度。
それでも4km/hでも衝突で突然停止したら、その衝撃による加速度(G)はかなり大きなものです。
しかし、このスロープシュータ、日常で大きな衝撃があります。
乗り場から、最高点まで登っていくチェーンに引っ掛けるところ。
シュターの車は動力がありませんので、係員が手動で、引き上げのチェーンのところまで押します。
チェーンには一定の間隔で爪が上に出ており、この爪が車両下部に引っかかると、ドッカンという大きな衝撃で上へ引き上げます。
この衝撃たるやかなり大きなもので、目視ですが、かなりの加速度(G)の様子。
スロープシューターの乗り場
![]()
乗り場出たところ。
![]()
これが上へ引き上げる鎖。
![]()
鎖の一定間隔に爪が出ており、
![]()
この鎖の爪が車の引っ掛ける部分と衝突して、車を上へ引き上げます。この時の衝撃がとても大きい。
![]()
「線路空間」いわゆる「側方案内軌条式」です。
![]()
![]()
「軌道桁」
![]()
観覧車の扉閉め忘れは、全くの係員うっかりですね。
しかし扉が開いていることが分かっても、他のお客さんがいるから、というのは、わけが分からない理由です。
ただ、よしんば止めたとしてもどうするべきだったでしょうか。
まだ全体の8分の1周にも達していなかったそうですが、地上からかなり離れた状態。
観覧車の構造はよくわかりませんが、逆回しはできないと思います。多分、お客さんのバランスを考慮して、逆方向のウェイトがかかってもストッパーが働くような構造ではないかと思います。工業的な考えでは。
なので、梯子をかけて係員を登らせて扉を閉めるか、それが出来なければ一周させなければならないのかもしれません。
東山動植物園は前にも書いた通り、名古屋市の組織にありがちな、形式的な石頭構造。
遊園地は、大部分がアルバイト係員だと思いますが、組織が硬直した体質だと、そこの従業員も硬直した考えで、柔軟な発想が出来なくなります。
決まり切ったことだけを反復しているだけだと、場合によっては行動に「漏れ」が起こり得ます。
その「漏れ」が、扉閉め忘れのうっかりです。
このために、東山動物園の遊園地は全ての遊具が、休止になったとのこと。
折角の東山動植物園春まつりの期間中なのに、非常に残念なことです。
記事

観覧車の搬器扉閉め忘れは、テレビのニュースで何度も伝えられました。
子供、と言っても中学生から幼児までの四人が乗った搬器、乗り場から出て行ったところを写そうとした母親が、扉が開いているのを見つけ、係員に停止を求めたものの、他のお客さんもいるから、というワケの分からない理由で、止めなかったそうです。
スロープシューターは、二人乗りの小さなエンジンの無いソリのような乗り物で、乗り物よりも少し幅の広い凹形の空間を、高低差の位置エネルギーだけで転がっていく乗り物で、レールが無いものの、凹の空間が線路空間みたいで、私の鉄ヲタエネルギーがうずうず?する乗り物です。
前を行く車が、なぜか途中で止まってしまった、ということですが、実際にあるんですね。
ジェットコースターだと、線路上に一編成しか存在しないか、或いは乗り場から出て行った編成が到着するまで、別の編成が出発できない構造なのですが、このシューターでは、特に「閉塞」のようなものは無く、時間間隔で乗り場から随時発車します。
前記の通り、鉄ヲタ精神で見ていると、「もし途中で止まってしまったら、後続車は衝突するしかないな」、と思いましたが、本当にそんなことが起こってしまいました。
ただ衝突、といっても走行速度はかなりゆっくりで、目測4km/h程度。
それでも4km/hでも衝突で突然停止したら、その衝撃による加速度(G)はかなり大きなものです。
しかし、このスロープシュータ、日常で大きな衝撃があります。
乗り場から、最高点まで登っていくチェーンに引っ掛けるところ。
シュターの車は動力がありませんので、係員が手動で、引き上げのチェーンのところまで押します。
チェーンには一定の間隔で爪が上に出ており、この爪が車両下部に引っかかると、ドッカンという大きな衝撃で上へ引き上げます。
この衝撃たるやかなり大きなもので、目視ですが、かなりの加速度(G)の様子。
スロープシューターの乗り場

乗り場出たところ。

これが上へ引き上げる鎖。

鎖の一定間隔に爪が出ており、

この鎖の爪が車の引っ掛ける部分と衝突して、車を上へ引き上げます。この時の衝撃がとても大きい。

「線路空間」いわゆる「側方案内軌条式」です。


「軌道桁」

観覧車の扉閉め忘れは、全くの係員うっかりですね。
しかし扉が開いていることが分かっても、他のお客さんがいるから、というのは、わけが分からない理由です。
ただ、よしんば止めたとしてもどうするべきだったでしょうか。
まだ全体の8分の1周にも達していなかったそうですが、地上からかなり離れた状態。
観覧車の構造はよくわかりませんが、逆回しはできないと思います。多分、お客さんのバランスを考慮して、逆方向のウェイトがかかってもストッパーが働くような構造ではないかと思います。工業的な考えでは。
なので、梯子をかけて係員を登らせて扉を閉めるか、それが出来なければ一周させなければならないのかもしれません。
東山動植物園は前にも書いた通り、名古屋市の組織にありがちな、形式的な石頭構造。
遊園地は、大部分がアルバイト係員だと思いますが、組織が硬直した体質だと、そこの従業員も硬直した考えで、柔軟な発想が出来なくなります。
決まり切ったことだけを反復しているだけだと、場合によっては行動に「漏れ」が起こり得ます。
その「漏れ」が、扉閉め忘れのうっかりです。
このために、東山動物園の遊園地は全ての遊具が、休止になったとのこと。
折角の東山動植物園春まつりの期間中なのに、非常に残念なことです。