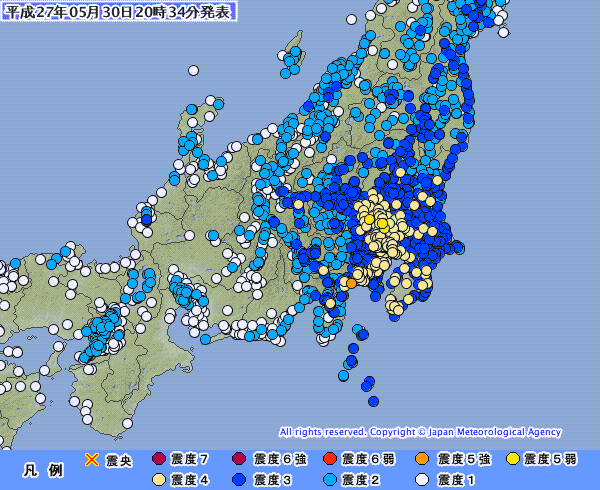京都市交通局の地下鉄とバスは、幼児の運賃(局では「料金」と案内)について、6月1日からは同伴者(保護者)一人に対して、全ての幼児を無料にするとのことです。
毎日新聞web版記事:京都市:市営地下鉄と市バス 保護者同伴で幼児みな無料に
現在は同伴者(保護者)一人について、幼児二人までが無料を人数の制限を撤廃しようというもの。三人目からは小児運賃です。
子育て世代の費用負担を抑えるのが目的とのこと。
京都市交通局でも同じく案内がでております:http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000182945.html
これによれば、従来の解釈であれば、同伴者一人に対して幼児二人までが無料、ということですが、この交通局の案内では「保護者」に連れられて、とあり、その保護者とは父母など親権者だとのこと。
なので、祖父母や、近所のおじさん・おばさんんに連れられて幼児が何人か乗る、というのはダメなのですね。こういう場合は、従来通り同伴者一人で幼児二人までが無料とのこと。
無料なのは、あくまで保護者同伴とされているので、幼児の単独乗車は小児運賃になります。これは現行規則でもあります。
この制度は子育て世帯の費用逓減とのことですが、京都市営の地下鉄とバスだけで、同じく京都市内の民間鉄道とバスは適用されませんし、幼児の小児運賃扱いについて、事業者によって違うので、その辺りを少なくとも地域ごとに統一されたいものです。
毎日新聞web版記事:京都市:市営地下鉄と市バス 保護者同伴で幼児みな無料に
現在は同伴者(保護者)一人について、幼児二人までが無料を人数の制限を撤廃しようというもの。三人目からは小児運賃です。
子育て世代の費用負担を抑えるのが目的とのこと。
京都市交通局でも同じく案内がでております:http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000182945.html
これによれば、従来の解釈であれば、同伴者一人に対して幼児二人までが無料、ということですが、この交通局の案内では「保護者」に連れられて、とあり、その保護者とは父母など親権者だとのこと。
なので、祖父母や、近所のおじさん・おばさんんに連れられて幼児が何人か乗る、というのはダメなのですね。こういう場合は、従来通り同伴者一人で幼児二人までが無料とのこと。
無料なのは、あくまで保護者同伴とされているので、幼児の単独乗車は小児運賃になります。これは現行規則でもあります。
この制度は子育て世帯の費用逓減とのことですが、京都市営の地下鉄とバスだけで、同じく京都市内の民間鉄道とバスは適用されませんし、幼児の小児運賃扱いについて、事業者によって違うので、その辺りを少なくとも地域ごとに統一されたいものです。